服務規律とは?社労士が労務リスクマネジメントの観点から解説

特定社会保険労務士の尾鼻則史です。
就業規則の一部として定められることが多い従業員の行動規範を「服務規律」と呼びます。行動規範というと、法令・規則の遵守義務についての訓示や心構えを想起しがちです。しかし「服務規律」にはそれ以外にも、労働者の就業や職場のあり方に関する規定(「狭義の服務規律」と言われる)、企業財産の管理や保全のための規定、従業員としての地位や身分に基づく規定等が含まれます。
これらの規定は単なる訓示や心構えとして機能するのではなく、場合によっては、労務リスクマネジメントという実務にも大きく関わってきます。
本記事では、「服務規律」を労務リスクマネジメントの観点から掘り下げたいと思います。
そもそも服務規律とは? 就業規則との違い
服務規律は、冒頭に記したように端的に言えば従業員の行動規範となるものです。そして一般的には就業規則の一部として規定されますが、就業規則そのものではありません。就業規則には、絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない「労働時間」「賃金」「退職」3項目に関する定め)と相対的必要記載事項(制度を設けて実施している場合には記載しなければならない事項)が含まれるからです。
また、賃金規程や育児介護休業規程のように、服務規律は就業規則に委任規定を設けて「服務規程」として別規程化することも可能です。
特定社会保険労務士の尾鼻則史のワンポイント
労務リスクマネジメントの観点からは、就業規則の相対的必要記載事項である「懲戒」の根拠として「服務規律」を用いるのが一般的です。そのため従業員への周知等を踏まえても、別規程や誓約書に記載するより、就業規則の一部として規定する方が、分かりやすいものとなるでしょう。
服務規律の目的
一般的に服務規律を定める目的は「企業秩序の維持」にあるとされています。企業が経営目的を遂行するために、その構成員たる従業員を統制・管理することが企業秩序の維持活動です。服務規律の規定・運用はその重要な手段であると言えるでしょう。
近年では、経営目的の遂行を阻害することになるハラスメントや情報漏洩など、法令遵守に留まらないコンプライアンス違反の防止を目的とした規定を設けるなど、服務規律の対象はより広範になりつつあります。
服務規律の内容
既述のように、服務規律には、法令や規則の遵守義務の訓示や従業員としての心構え以外に、労働者の就業や職場のあり方に関する規定、企業財産の管理や保全のための規定、従業員としての地位や身分に基づく規定等が含まれます。
一般的に定められる服務規律
従前から一般的に規定されることの多い具体例を示すと以下になります。
【労働者の就業や職場のあり方に関する規定(狭義の服務規律)】
・企業施設への入退場に関する規定(勤怠記録、身分証明書携帯等)
・私物の持ち込みや所持品検査に関する規定
・遅刻、早退、欠勤、休暇の報告、それらの届出・許可手続の規定
・就業中の離席、外出、面会の規制、それらの届出・許可手続の規定
・服装や身だしなみに関する規定 など
【企業財産の管理・保全のための規定】
・企業所有物品の持ち出し
・流用の禁止規定
・火気取締り規定
・消耗品の節約等に関する規定
・企業施設を利用した会合
・活動の制限規定
・企業施設内での文書の掲示
・配布の制限規定 など
【従業員としての地位・身分に基づく規定】
・企業の名誉
・信用保持規定
・兼職・兼業・副業に関する規定
・公職就任等に関する規定
・秘密保持規定
・身上異動等に関する規定 など
近年規定されるようになった服務規律
服務規律には、社会情勢の変化、雇用社会の変容に対応し近年設けられるようになった規定もあります。具体例としては以下があります。
【労働者の就業や職場のあり方に関する規定(狭義の服務規律)】
・ハラスメント禁止規定(セクハラ、パワハラ、マタハラ、パタハラ、ケアハラ等の禁止)
・テレワーク・在宅勤務規定(勤怠、情報取扱い、職務専念、端末およびネットワーク利用)
・私物情報端末利用制限規定(私物のPCやモバイル端末の業務使用の原則禁止、使用許可等)
・SNS適正利用規定(会社の信用失墜に繋がる情報発信の禁止、技術・営業・経営上の機密情報発信の禁止等)
【企業財産の管理・保全のための規定】
・会社情報端末適正利用規定(業務外目的使用の禁止、セキュリティ対策の義務づけ、パスワードの設定・管理等)
・社内情報システム適正利用規定(電子メール・インターネットの業務外目的使用の禁止等)
【従業員としての地位・身分に基づく規定】
・個人情報保護に関する規定(個人番号を含む個人情報の不正取得・業務外取得の禁止、法定外の情報開示・提供の禁止、複製の禁止、アクセス権を超える利用の禁止、情報漏洩等の管理責任者への報告、配転・退職に伴う情報の返却等)
・競業避止義務
・反社会的勢力排除規定
キテラボ編集部よりワンポイント
規程管理システム KiteRa Bizは、約120規程雛形をご用意しております。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。
【規程管理システム KiteRa Bizの詳細は下記リンクからご覧ください。】
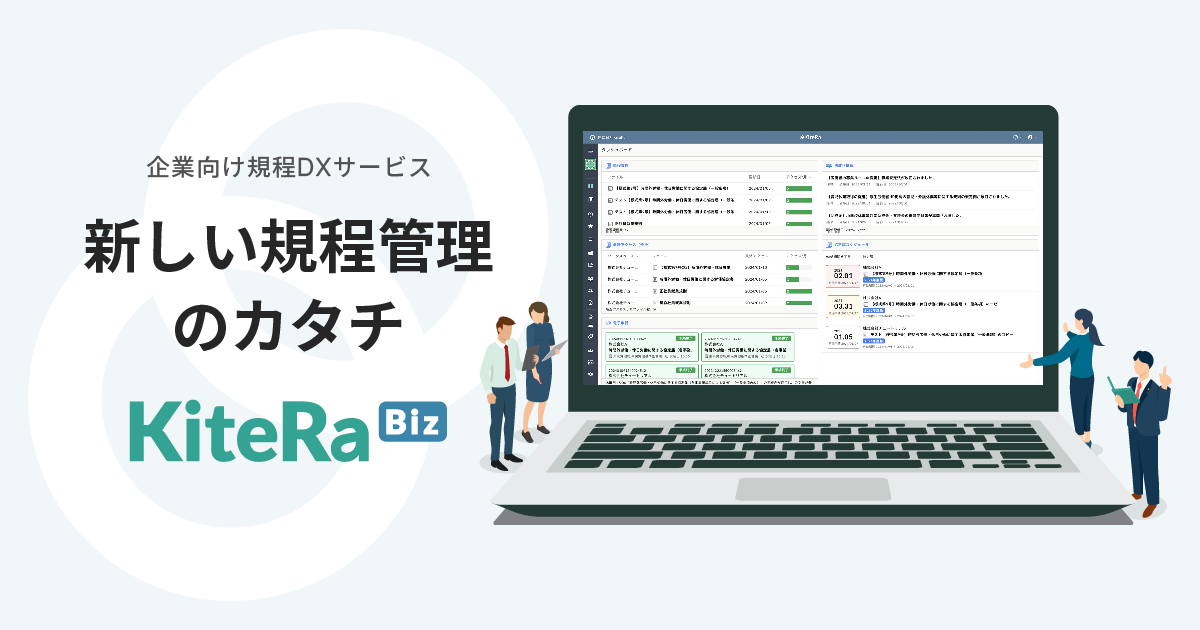
新しい規程管理のカタチ!社内規程DXサービス
社内規程DXサービスとは、社内規程の作成・編集・管理・共有・申請の一連のプロセスを統合管理するシステムです。統合管理することで各プロセスの業務を効率化し、企業のガバナンス向上を実現します。
規程管理システムとは!?社労士が人事労務担当者向けにメリットを解説します
規程管理システムとは、各企業が独自に定める社内ルール「社内規程」の作成・改定・管理を行うためのシステムのことです。専用のシステムを使うことで、効率的かつスムーズな作業が実現できます。
企業独自の服務規律
◆船内恋愛禁止
SNSでは東幸海運のケースが大きな話題になりましたが、海運会社の中には、社内恋愛は禁じていないものの、海の上での共同生活となる船内での恋愛を禁止する服務規律を置いている会社があります。男女が同じ船に乗って問題が起きたら逃げ場がないためで、男女でドアの閉まった部屋に入ると強制下船という厳格な運用もなされているようです。
◆あいさつ義務
金融機関、病院など上位下達の色濃い組織では、あいさつ義務を服務規律に掲げているケースも少なくありません。秩序維持のための「訓示」として服務規律に残存している事業所も多数あるのが実態でしょう。
◆ひげ、ピアス、茶髪NG
金融機関を中心に、身だしなみの中でも、より具体的にこれらを禁じる服務規律を定めている企業は少なくありません。これらの禁止事項が「合理的」と裁判所で判断される間は、懲戒処分を科すことも可能でしょう。
服務規律の注意点
服務規律は、規定すれば如何なるものも効力は発揮するわけではありません。企業および労働契約の目的上必要かつ合理的である限りにおいて認められます。裁判所は服務規律に基づく懲戒処分の有効性判断において、服務規律の諸規定について合理的な内容に限定解釈するなどしています。服務規律にも限界があると認識しておく必要があります。
特定社会保険労務士の尾鼻則史のワンポイント
さらに、服務規律違反に基づく懲戒処分の裁判所の判断に際しては、準用や類推適用の必要のない規定であればある程、有効と判断される蓋然性は高くなります。つまり、可能な限り網羅的に服務規律を定める方が、リスクマネジメントとしては優れていると言えそうです。
服務規律の変更
服務規律見直しの必要性
服務規律については絶えざる見直しが必要です。既述のようにに可能な限り網羅的に服務規律を規定することはリスクマネジメント上有益です。また企業秩序維持のための非違行為の「抑止力」としても、できるだけ個別企業の実情に沿って具体的に網羅されている方が効果的でしょう。
そのため、重大な非違行為が生じた場合にはその都度、重大でなくとても再発の蓋然性があり看過すべきでない非違行為については定期的に、服務規律化していくことが不可欠です。
変更の手順
服務規律の変更は、就業規則の変更ないし委任規定に基づく服務規程の変更に当たりますから、以下の手続きを経る必要があります。
①変更案について労働者代表の意見聴取
②「意見書」の作成
③「就業規則変更届」「変更後の就業規則」の準備
④所轄労働基準監督署への届出
➄従業員への周知(職場への掲示又は備え付け、書面交付、データとして閲覧等)
服務規律に違反した場合の対応
服務規律違反を懲戒の根拠・基準として定めていることを前提として、事実確認を下記のように行います。ただし、ケース・バイ・ケースで項目をスキップする場合もあり、項目が追加されることもあります。
①服務規律違反行為の告発者等へのヒアリング
②証拠の収集
③告発者等以外の関係者へのヒアリング
④服務規律違反行為を行ったと見られる者へのヒアリング
事実確認は「予断を持たず」「中立的に」行われるプロセスの確保が重要です。従って、事実認定をどのようなメンバーで行うのか、最終的な懲戒処分の決定をどこで(取締役会等)行うのか等についても予め決定し、就業規則の「懲戒」において規定しておくことが望まれます。
特定社会保険労務士 尾鼻からのアドバイス
ここまでのオーソドックスな議論以外にも、一般にはあまり論じられないものの、深刻な労務リスクが高い服務規律の関連テーマは存在します。
例えば、従業員同士の私的な交際に端を発して企業秩序が害されるようなケースです。特に不倫を含む交際トラブルは何れの企業でも起こり得るもので、職場環境を著しく悪化させるクリティカルな問題です。
他方で、私的な交際に服務規律で何らかの直接的な規制をかけること、さらにはそれに基づいて懲戒処分を行うことは困難です。労働契約法15条でも「当該懲戒が、…、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定められています。
では、このような事案にはどう備えるべきでしょうか。裁判例としては、社内不倫を理由として実質的に懲戒解雇相当であることを認めたものがあります(東京高等裁判所昭和41年7月30日判決)。これによれば「不倫関係が、それ自体職場の秩序を著しく乱す行為であり、これによって現に当該女性車掌を退職させ、他の女性従業員に対して不安と動揺を与え、さらに求人についての悪影響等をもたらしたこと」「会社の社会的地位、名誉、信用等を傷つけるとともに、正常な業務運営を阻害し、運営会社に損害を与えたこと」が有効とした理由として挙げられています。
この判例を踏まえれば、現代的に男女交際に限定せず、「従業員間の私的な交際に伴って、職場の風紀・秩序を乱してその環境を悪化させ、正常な企業運営を阻害してはならない」と定めることは可能でしょう。「職場環境の悪化」「企業運営への実害」を介することで間接的に規制をかけるわけです。
実際に懲戒処分を科すか否かは情状次第でしょうが、少なくとも「抑止力」として、この種の服務規律を置くことは、多くの企業に対してアドバイスさせて頂いているところです。